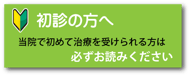インプラント治療が変わる
日常歯科臨床と再生医療の架け橋
組織工学は科学の新しい分野であり、その最終ゴールは再生治療です。
欠損あるいは、機能不全の体の一部を材料で置き換えるかわりに、組織あるいは器官を再生させることが最終目的です。
歯科においてはいくつかの再生医療が既に臨床応用され始めており、基礎研究の分野では歯の再生を含む口腔組織の再生への数々のアプローチがなされています。
このような今日の状況において 再生医療がインプラント治療をはじめとして、いかに日常臨床に かかわっているかという視点でこれからの10年間における歯やその付近の骨の欠損を持つ患者さんに対する治療について発信できればと思います。
患者さんの血液と骨髄液で骨を作り、お口の中の欠損部分に移植
この術式に、私がドイツに渡って8人のドイツ人の方のオペに2009年立ち会いました。
ドイツフライブルグ大学で世界に先がけて研究された再生医療の実際です。患者さんの血液と骨髄液を使ってオペ室の中で30分で骨の幹細胞を作り、それをベースとして骨を創り、お口の中の骨の欠損部に移植します。
つぶさに体験したフライブルグ大学オペ室と研究室での流れを皆様にご報告いたします。当院でのインプラント治療などに1部応用導入しつつある再生医療の一端を垣間見ていただければと思います。

移植オペの流れ

腸骨穿刺(左)から得た骨髄液を、遠心分離機にのせるためのBMAC容器(右)
脇に見えるのが抗凝固処置のためのヘパリンとクエン酸塩による前処置用器材。


手術室の中で使用することができる遠心分離機。
血液の凝固を起こす酵素である自家トロンビンを得るための処理は、患者様から得た静脈血を8㏄入れてカウンターウエイト(青色)の中に入れられ、そこは遠心分離沈殿用ダブルチャンバーの反対側に位置する。そして自家トロンビンを作り出します。


骨髄液と静脈血は遠心分離され、ダブルチャンバー内右側の大きなチャンバー側の中は赤血球が保たれる。一方、左側の小さなチャンバーには白血球細胞などと血小板に分離される。
左側の小さなチャンバーの黄色又は琥珀色の上澄みを捨てた後には著者が指差した所に「Buffy Coat」と呼ばれる青白い黄色の帯が現れる。
この青白い黄色の帯は白血球・単核細胞などで構成され、この層の下に血小板がある。この最下層に沈殿した血小板が最も濃厚で良質です。


遠心分離後、上澄みの液の大部分は捨てられる。
上澄みの下の「Buffy Coat(青白い黄色の帯)」を狙って、6~7㏄をゆっくり回転させながら吸い上げていく。
これが最も重要な部分で、骨髄性幹細胞が濃縮されたものです。


約14分の遠心分離機の回転により、HAT-Kitから得られたトロンビンはビニールの滅菌パックに包まれる。


ピストル型のハンドグリップは2本のシリンジを均等に押すための付属品。
この1本は、BMACが3㏄、もう一本も自家トロンビンが1㏄。
この3:1の比率でピストルを押すと、トロンビン塩化カルシウムを放出し混合されて凝固する。
凝固するとただちに成長因子の放出が始まる。


放出された成長因子は容器に入っている移植材(このケースではBIO‐OSS)との混合物を作る。
その混合物は手術部位への移植の準備に入る。


混合されたもの
「Bone-Grafting材」このケースでは、「Bio-Oss(Geistlich)」が 「scaffold」 となる。


上あごの骨が薄すぎてインプラントを入れるには無理のある、骨のない部分に増す為、骨を上顎洞の中に造る。
その骨移植材としての混合物を上顎洞の横に開けた窓(ラテラルウィンドウ)から充填する。
そして数ヶ月たった上顎洞内の新生骨にインプラントを入れて人工の根(人工歯根)とする。
出典:ドイツ・フライブルグ大学におけるボーン・グラフティングの実際
「2009年11月高度先進歯科医療を学ぶ」土肥著より
将来的な展望
東京理科大学生物工学部の発表によれば、歯胚(歯のもとになるもの)に由来する上皮・間葉組織の単一化細胞から人工的な歯胚を再構築する器官原基法を開発したとの事です。
この人工的な歯胚は生体内移植モデルや生体外器官培養において正常な歯を形成するとともに、口腔内の抜歯腔で血管や神経を有して初期発生することが可能であることを明らかにしています。
東京女子医大と早稲田大学工学部の共同研究では、口の粘膜の細胞から目の角膜を作ったり、抜歯する乳歯の歯根膜細胞を保存して、大人になって永久歯を失った時にとっておいたその細胞から、第2の永久歯を作ろうと研究しています。
これから10年間になるかそれ以上の未来になるかわかりませんが、歯の欠損患者様に対する治療もインプラントによるオステオインテグレーション(骨との融合)に代わって患者様自身の上皮・間葉系組織の細胞から新たな歯を再生する可能性は大きくあり、もはや夢物語ではなくなりそうです。
臨床応用が可能になるこの分野への目が離せません。

出典:「TMDC MATE 第267号」 2011年11月1日
症例別の治療
症例1:インプラントと咬合(かみ合わせ)治療
~ 身体や精神的不調も改善~
S・A 様 (1954年生まれ)

某大学歯学部付属病院で「前歯2本と左下臼歯の抜歯」を告げられ、歯を抜かないで治療する方法はないかと、当クリニックを探し来院。
歯科だけではなく身体の不調もあり、色々な検査をしても医師の診断は「異常なし」という結果でした。
歯を失っていて咬み合わせに大きなズレがあり、身体に影響がありました。
<治療の過程>

治療前の上あごの写真です。歯を失った後、そのままにしていて時間がたってしまい、咬み合わせが大きくずれてしまっています。

失った歯が原因で色々な問題が生じました(初診時主訴などの)。
生体力学的安定を求めたインプラントによる治療計画を立てました。

インプラントの上に冠を作って、咬み合わせの安定を計りました。
(咬み合わせ面から撮影した写真)

インプラントの上にある、本人の左上奥歯の5本の被せ物。
前の歯はグラグラだったのですが、何とか抜かずに安定しました。
(前から見える側から撮影した写真)

下あごの位置をスプリント(安定したあごの位置を求め、維持する歯の上に乗せる装置)から割り出して快適な位置にかえるという、3次元的位置でのリハビリテーション用テンポラリークラウン装着。

リハビリテーション用ファイナルクラウン
(ご自身の歯に酷似した被せ物)の装着。
※ 御自身の歯は全く削っていません
<治療結果>

最小限の本数のインプラントによる被せ物が入った事であごの偏位が改善されると、首の骨の配列も改善され、左右の椎骨脳底動脈の循環不全が解消され、脳への血流が上がります。
また、体の重心軸が整い、頭がうつむきかげんから自然な姿勢に戻ります。治療前の不定愁訴の症状がほとんど消えました。
症例2:歯の移植(親知らずをインプラントの代わりに使う)
~インプラントをしないでご自分の歯の移植で失った歯の再生をする~
<初診時>

1987年4月18日(初診時)
オルソパントモX-Ray写真像

1987年4月27日
左から、正面、上あご、下あごの状況
<移植時>
右下奥歯8番目の親知らずを右下奥歯6番目に移植

左 :歯の移植前(1997年2月22日)
中央:歯の移植時(1997年5月14日)
右 :移植前後の記録
<途中経過>

左:移植1年後(1998年5月13日)
右:移植6年後(2004年9月17日)
<術後14年>

Before 1987年 After 2011年

2011年1月13日
骨の移植(造骨を大切にしたインプラント治療)
ご高齢の方の生活の質を高める事が可能となります。